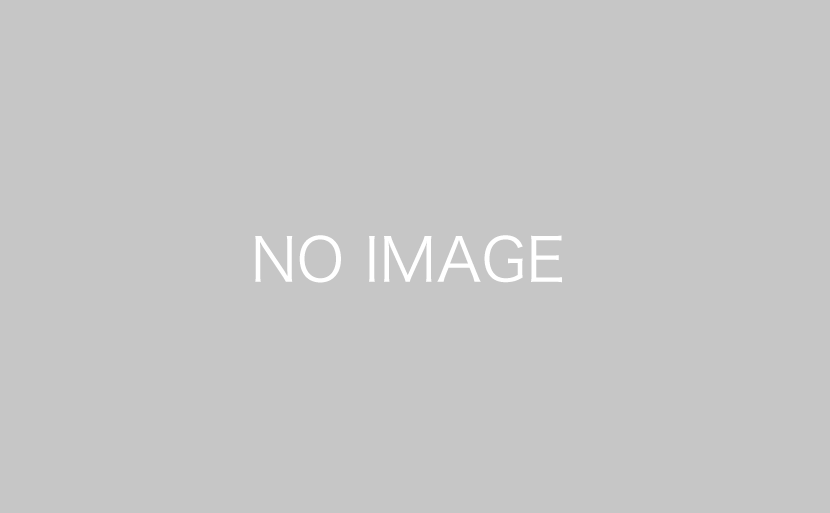この記事の要約
- 予防を開始したら、3か月は続けたほうがよいですが、症状がなければ、延々と使い続ける必要はありません。
- こまめに喘息を評価し、現在の状態に最も適切な治療を選択することが大事です。こうすることにより、不必要な治療を防ぐこともできます。
- まずは、どの程度の間隔で発作がおこり、その発作の強さがどの程度か知る必要があります。
- つぎに、今受けている治療がどの程度なのかを理解してください。
- そして、現在の治療は効果があるのかを確認しましょう。発作が続く場合は、治療を一段階上げ、3か月以上落ち着いている場合には、治療を一段階下げていきます。
「喘息の診断を受けて薬を飲み始めたけれど、いつまで飲めばいいのですか?」というご質問を保護者の方から受けることが多くあります。結論から言うと漫然と薬を飲み続ける必要はない場合があります。症状の頻度や症状の程度を受診のたびに評価して今の治療が適切なのかを判断する必要があります。大体治療を開始して、3か月後の状態を評価して今後の治療を増やすのか、減らすのかを決めていくことが、日本小児アレルギー学会が推奨するガイドラインに記載されています。
症状がないのに何年も内服を続けることは推奨されておりませんし、必要もありません。今回は具体的に、喘息の治療をいつまで続けるのがいいのか、喘息はどのように薬を使ってコントロールしていくのかを解説します。
第1段階から第4段階まで、一つずつ理解して、判定してください。お子さんの状態を正しく理解することが、喘息の適切な治療につながります。
喘息の重症度
まずは、現在の喘息の重症度を評価することが必要です。
| 重症度 | どの程度の発作がどのくらいの頻度ででているか? |
| 間欠型 | 軽い症状が年に数回(風邪をひいた時だけ、季節の変わり目だけ) メプチン、ベネトリンなどの吸入薬を使用することで短時間で改善し、それが持続しない |
|---|---|
| 軽症持続型 | 軽い症状が月に1回から週に1回未満 ときに呼吸困難あり、日常生活に支障は出ていない |
| 中等症持続型 | 軽い症状が週に1回以上から1日に1回未満 ときに大・中発作となり、日常生活でできないほどになる |
| 重症持続型 | 毎日発作がでる、週に1〜2回大・中発作となり、日常生活が難しい 治療をしても、しばしば症状が悪くなってしまう |
| 最重症持続型 | 多くの治療を行っても症状が持続してしまう しばしば時間外に医療機関を受診し、入退院を繰り返し、日常生活が制限されてしまう |
治療ステップ
どのような治療を受けているかも本当の重症度を判定する上で重要です。
現在、喘息治療のどの段階にいるのかを判断します。次に示す表から治療ステップの1~4のどの段階にいるのかを判断しましょう。
| 長期管理 薬物療法 プラン |
ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 | ステップ4 | |
| 2歳未満 | 基本治療 |
発作の強度に応じた薬物療法 (毎日内服吸入なし) |
オノン、シングレア、キプレスの毎日内服 and/or インタールの毎日内服・吸入 |
吸入ステロイド薬(中用量)毎日吸入 | 吸入ステロイド薬(高用量)の毎日吸入に、オノン、シングレア、キプレスの毎日内服併用も可 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2歳〜5歳 | オノン、シングレア、キプレスの毎日内服 and/or インタールの毎日内服・吸入 and/or 吸入ステロイド薬(低容量)毎日吸入 |
吸入ステロイド薬(高用量)の毎日吸入に、オノン、シングレア、キプレスの毎日内服、テオドールの内服、メプチン、ホクナリンテープの併用。 もしくは、アドエアへの変更 |
|||
| 6歳〜15歳 | 吸入ステロイド薬(低容量)毎日吸入 and/or オノン、シングレア、キプレスの毎日内服 and/or インタールの毎日内服・吸入 |
吸入ステロイド薬の用量対比表(1日量で記載)
| 低用量 | 中用量 | 高用量 | |
|---|---|---|---|
| フルタイド、キュバール、オルベスコ、アドエア | 〜100μg | 〜200μg | 〜400μg |
| パルミコート吸入液(吸入器使用) | 〜0.25mg | 〜0.5mg | 〜1mg |
※フルタイド50を1日2回吸入なら100(低用量)としてみてください。
※パルミコート0.5mgを吸入器で1日1回なら0.5mg(中用量)、1日2回なら高用量になります。
本当の重症度を判定する
治療ステップがどの段階にいるのかと第1段階で判断した重症度を組み合わせ、現在の治療内容を踏まえた上での本当の重症度を判定します。
| 第一段階 | 治療ステップ1 | 治療ステップ2 | 治療ステップ3 | 治療ステップ4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 間欠型 | 間欠型 | 軽症持続型 | 中等症持続型 | 重症持続型 | |
| 軽症持続型 | 軽症持続型 | 中等症持続型 | 重症持続型 | ||
| 中等症持続型 | 中等症持続型 | 重症持続型 | 最重症持続型 | ||
| 重症持続型 | 重症持続型 | ||||
| 最重症持続型 | 最重症持続型 | 最重症持続型 | 最重症持続型 |
第1段階から第2段階まで評価し、最後に第3段階の表にあてはめる。
例 ①喘息発作が月に1回くらい出ている・・・第1段階の表にて → 軽症持続型
②3歳で、オノンのみ飲んでいる ・・・第2段階の表にて → 治療ステップ2
③第3段階の表で、縦:軽症持続型、横:治療ステップ2を見てみる → 「中等症持続型」と判断する。
喘息治療がうまくいっているかを判断します!
喘息のコントロールがうまくいっているかを評価し、それによって治療法を変更します。
喘息発作について以下の表の項目で評価します。1か月間のコントロール状況を診察時に判断し、コントロール良好が3か月以上続けば、治療ステップを一段階下げることを考えます。このときに、季節の変化や入院の既往、重篤な発作の既往などの将来的な症状の悪化も考慮して、長期的な治療計画を立てていきます。
| 評価項目 | コントロール状況 | |
|---|---|---|
| 良好 | 比較的良好 | |
| 軽微な症状 | なし | 月に1回以上、週に1回未満 |
| 明らかな喘息発作 | なし | |
| 日常生活の制限 | なし(あっても軽微) | |
| β刺激薬(メプチン、ベネトリンなど)の使用 | 月に1回以上、週に1回未満 | |
まとめ
- お子さんの喘息がどのくらい悪いものなのか(重症度)を知りましょう。
- 現在の治療法がどの段階にいるのかを確認しましょう。
- 現在の治療が効果があるのか、医師と共に確認しましょう。コントロールができていない場合は、治療ステップを一段階上げ、3か月以上コントロールできている場合には、治療ステップを一段階下げましょう。
こまめに喘息の評価をすることで、不必要な内服を防ぐことができ、現在のお子さんの状態にあった治療法を選択することができます!
クリニック一覧はこちら
お子さまの体調や気になる症状があるときは、無理せずお近くのクリニックへご相談ください。地域に根ざした小児科として、日々の診療を行っています。
キャップスクリニックの特長

①365年中無休で朝9時~夜21時まで診療(一部クリニック除く)
キャップスクリニックでは、「標準的な治療」を365日受けることができる「治療提供拠点」を維持し、普及することに努めています。
日々お忙しい中でも安心してご受診いただけるよう、朝9時~21時まで開院しております(一部クリニックを除く)。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆なども休まず診療しておりますので、いつでもご来院ください。
②ご家族の皆さまもご一緒に!
小児科でも、お子さまとご一緒にご家族の皆様も診察・予防接種等をお受けいただけます(受診される方全員のご予約・ネット問診をお済ませください)。
※ご症状によっては内科受診をお勧めさせて頂く場合がございます。
また、当院は24時間ネット予約受付システムを運営しており、いつでもご予約および事前問診が可能です。ご家族の皆様で同じお時間にまとめてご予約していただくことも可能となっております。
ご家族の皆様が同じ時間に予約する方法
③1枚の診察券で全クリニックをご受診いただけます
複数クリニックに展開しているキャップスクリニックを、共通の診察券でご受診いただけます。
④予防接種、各種健診を毎日実施しています
一般的に、予防接種は乳児健診などは曜日が限定されているクリニックが多い中、キャップスクリニックでは予防接種・健診を毎日実施しています(事前予約が必須)。
原則、当院は朝から21時まで診療しておりますので、お忙しい中でもご都合のよいタイミングでご来院いただけます。